賃貸契約のとき、「連帯保証人を立ててください」と言われることがあります。
頼れる家族がいない、遠方に住んでいるといった理由から、友人に頼みたいと考える人も少なくありません。
この記事では、連帯保証人に友人がなれるのかどうか、必要な条件や引き受ける側のリスクについて解説します。
連帯保証人に友人はなれるの?
結論から言えば、友人でも連帯保証人になることは可能です。
ただし、誰でもOKというわけではなく、一定の条件を満たしていることが前提となります。
一般的な条件は以下の通りです:
- 安定した収入がある(会社員・自営業など)
- 20歳以上の日本国籍を持つ人
- 契約者と連絡が取れる関係性であること
- 過去に大きな信用事故(債務整理・滞納など)がないこと
保証会社を利用しない物件や、家主の意向によっては「家族限定」とされることもあるため、事前確認が必要です。
連帯保証人が負う責任とは?
「名前を書くだけ」と思いがちですが、連帯保証人の責任は非常に重く、契約者と同等の支払い義務を持ちます。
つまり、契約者が家賃を払えなくなったときは、連帯保証人が代わりに全額支払う必要があるということです。
主なリスク:
- 家賃・原状回復費・滞納金などの請求が一括で来る
- 支払いができなければ、連帯保証人自身の信用情報に影響が出る
- トラブルになった場合、人間関係が壊れるリスクも
特に長期契約の場合、契約終了まで責任を負うことになるため、軽い気持ちで引き受けないことが大切です。
友人に頼むとき・引き受けるときの注意点
頼む側の注意点:
- 無理にお願いしない、引き受けたくない人に強制しない
- どのくらいの期間・金額を保証するのかを明確に伝える
- 感謝の気持ちを忘れず、保証解除のタイミングも共有しておく
引き受ける側の注意点:
- 契約内容や責任の範囲を事前に確認する(契約書・説明書を読む)
- 本当に信頼できる相手か、自分に支払能力があるかを考える
- 不安がある場合は、「保証人代行(保証会社)」をすすめるという選択肢も
まとめ
連帯保証人に友人がなることは可能ですが、責任の重さやリスクをしっかり理解したうえで判断することが必要です。
頼む側も引き受ける側も、事前にしっかり話し合い、お互いに納得したうえで契約に進むことが大切です。
どうしても不安な場合は、保証会社の利用を検討することで、お互いに安心して生活を始めることができます。

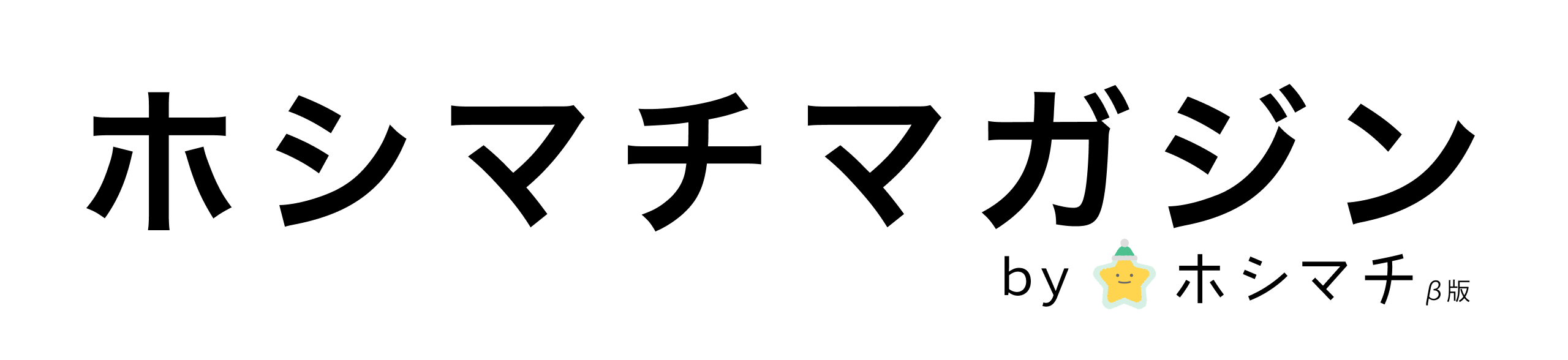



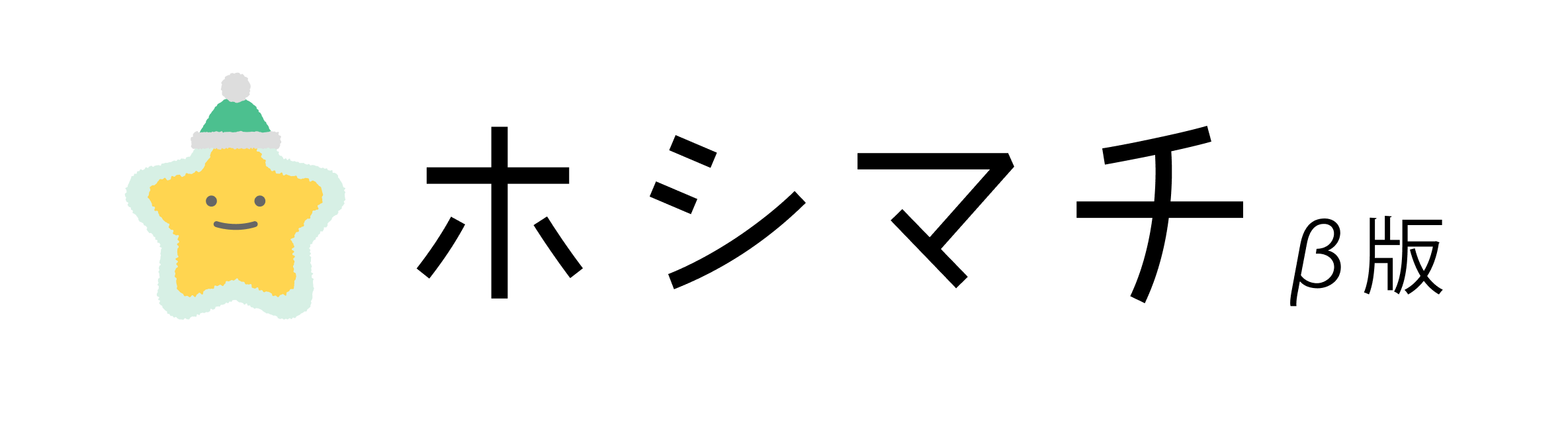
コメント